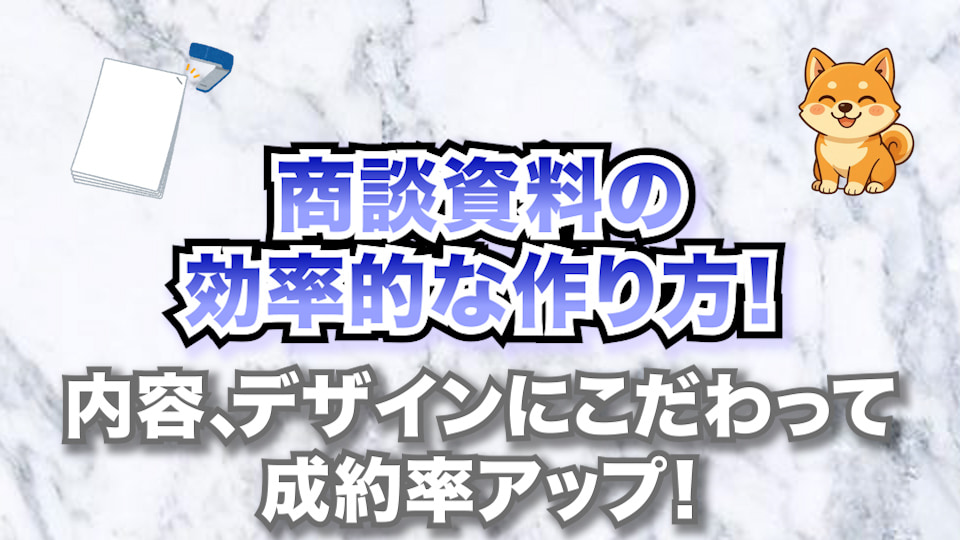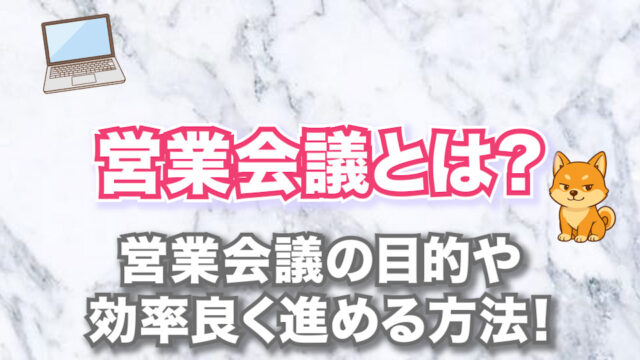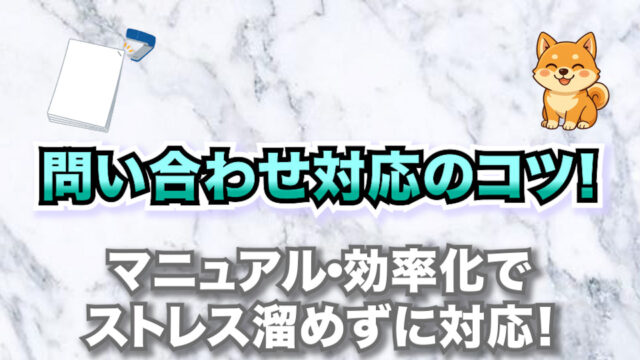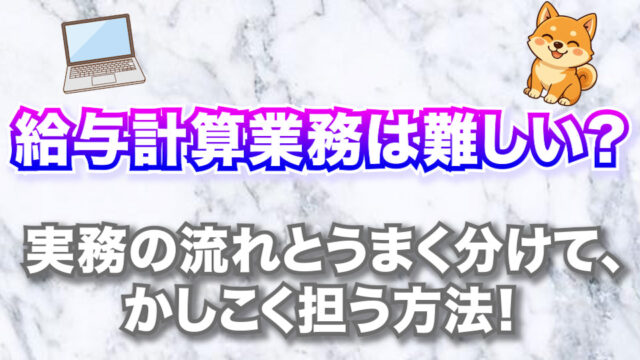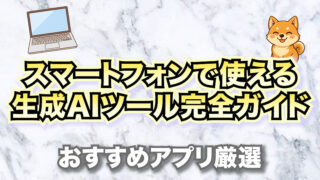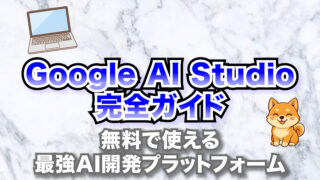商談資料は、営業先に交渉する材料として、非常に重要です。
いい資料を作るレギュレーションができていれば、会社や組織全体の成約率を上げることができるでしょう。
今回は、そんな商談資料の作り方について紹介していきます。
効率的にそして、営業先に刺さる商談資料の作り方を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
1.商談資料の準備

商談資料作成は、製品やサービスの概要、料金プラン、導入メリット、導入事例などを視覚的に伝える、営業活動において顧客との商談を成功させるための重要な業務です。
単なる会社案内や商品カタログとは異なり、商談資料は「特定の顧客の課題解決」に焦点を当てた個別対応の資料です。
顧客の業界、規模、抱える問題を分析し、自社の商品・サービスがどのように課題を解決できるかを論理的に示す必要があります。
他書類・他業務との違い
- 「提案書」は、特定の案件に対して条件や価格を詳細に記載するもの。一方、商談資料は“興味を引く”ことが主眼です。
- 「プレゼン資料」は場の演出に重点を置くのに対し、商談資料は“その場で読まれて伝わる”構成が重要です。
- 「マーケティング資料」は不特定多数向けですが、商談資料は特定の相手に“刺さる内容”に仕上げます。
つまり、商談資料は、営業担当者の提案力を支える重要な武器として、商談資料の品質が契約獲得に直結するため、事務職員のスキルが営業成果を大きく左右します。
デザイン性、情報の整理力、そして相手に響くストーリー構成が求められる、創造性と論理性を兼ね備えた業務といえるでしょう。
2.商談資料の基本構成と記載・実施項目

商談資料の基本構成は「課題提起→解決策提示→根拠→行動喚起」の流れで組み立てます。
具体的には、表紙、課題・ニーズ整理、解決策提案、事例紹介、料金・条件、次のステップの6つのセクションで構成されることが一般的です。
商談資料の基本構成
- 表紙(会社名、提案タイトル、日付)
- 課題・ニーズ整理(顧客の現状と困りごと)
- 解決策提案(商品・サービスの詳細)
- 事例紹介(類似企業での成功事例)
- 料金・条件(価格、契約条件、期間)
- 次のステップ(今後の進め方、スケジュール)
よくあるミスと対策
- 【ミス】情報を詰め込みすぎて伝わらない
→【対策】「1スライド1メッセージ」を意識して設計 - 【ミス】ターゲットに合わせた言葉選びができていない
→【対策】過去の商談資料や成功事例を参考にカスタマイズ
よくあるミスとして、自社商品の説明に偏りすぎて顧客メリットが不明確になることが挙げられます。
防止策として、各ページに「顧客にとっての価値」を必ず盛り込み、商品説明ではなく「課題解決手段」として表現することを徹底しましょう。
また、情報過多による読みにくさも頻発するため、1ページ1メッセージの原則を守ることが重要です。
3.商談資料通常業務フロー

商談資料作成は、次のようなステップで行われます。
- ヒアリング(営業担当者からの要望取りまとめ)
- 素材収集(サービス概要・事例・価格など)
- 構成案作成
- パワポ等でスライド作成
- 営業担当者との擦り合わせ・修正
- PDF化して共有
まず営業担当者から顧客情報と提案内容をヒアリングし、どのような課題を抱えているか、何を重視しているかを把握します。
次に資料の構成を検討し、どの順番で何を伝えるかの設計図を作成。
その後、実際の資料作成に入り、テキスト作成、グラフ・図表作成、デザイン調整を行います。初版完成後は営業担当者や上司とのレビューを経て、修正を重ねて最終版を完成させます。
このフローで最も時間がかかるのが「資料作成」の工程で、全体の60-70%の時間を要します。
特に、毎回ゼロからレイアウトを考える作業、適切な画像や図表の選択・作成、文章の推敲に多くの時間を費やしています。
また、営業担当者とのやり取りが多く発生し、認識齟齬による手戻りも課題となっています。
レビュー工程でも、フィードバックが曖昧で何度も修正を繰り返すケースが多く、効率化の余地が大きい業務です。
課題ポイント
- ヒアリングが曖昧だと作り直しが頻発
- 類似資料がどこにあるかわからず、毎回ゼロから作成
- デザイン調整に時間がかかる(特に図や表の整形)
4.商談利用の管理・運用上の注意点

商談資料の作成は、ナレッジの蓄積が肝です。以下の工夫で効率と再現性を高めましょう。
まず、過去の資料を効率的に検索・再利用できるよう、ファイル名の命名規則を統一します。
- 【整理】用途別・業種別などでフォルダ分類(例:[製造業向け][飲食店向け]など)
- 【検索】スライドタイトルやタグで検索できる管理表を作成
- 【管理】バージョン管理と更新履歴を残す(GoogleスライドやNotionの活用もおすすめ)
テンプレートやパーツの管理も重要です。よく使用する図表、文章表現、事例紹介などをデータベース化し、類似案件での再利用を促進します。
特に業界別のテンプレートを整備しておくと、作成時間を大幅に短縮できます。
バージョン管理では、修正履歴を残し、最新版がどれかを明確にする仕組みが必要です。クラウドストレージを活用し、営業担当者との共有をスムーズにすることで、リアルタイムでの確認・修正が可能になります。
また、機密情報を含む資料のため、アクセス権限の設定と定期的な見直しも欠かせません。
5.どこがAIに?“全部やる”から“うまく分ける”へ。

商談資料作成において、AIに置き換え可能な部分と人が残るべき部分を明確に分けることが、効率化成功の鍵となります。
AIが得意な領域は、定型的な構成作成、基本情報の整理、文章の初稿作成、デザインレイアウトの提案です。
AIで置き換え可能な部分
- テンプレートからの資料構成自動生成
- 顧客情報に基づく課題整理文の作成
- 商品説明文の初稿作成
- グラフ・表の自動作成
- デザインレイアウトの提案
人の手が必要な作業
- 提案方針やターゲットに合わせた構成判断
- 提案ストーリーの設計
- 説得力のある事例の選択
- 相手に響く表現への調整
- 最終的な品質チェック
人が残るべき部分は、顧客との関係性を踏まえた提案内容の調整、相手企業の文化や担当者の価値観に合わせた表現の微調整、競合他社との差別化ポイントの強調など、「人間らしい洞察力」が必要な領域です。
6.商談資料の業務効率化とオートメーションの具体策

ここからは、商談資料作成の際の業務効率化、オートメーションについて紹介していきます。
Before(手作業)After(AI活用)でわかりやすく紹介していきますので、しっかり確認していきましょう。
| 作業工程 | Before(手作業) | After(AI活用) |
| 類似資料検索 | フォルダ内を人力で探索 | キーワード検索+AIレコメンド |
| 構成の作成 | 過去資料からの手作業流用 | ChatGPTで構成案生成 |
| 文章作成 | 担当者が1から執筆 | 要点を入力してAIで草案作成 |
| デザイン仕上げ | PowerPointでの調整に時間 | Canvaなどでテンプレ活用 |
おすすめツール
- ChatGPT(文章生成・構成提案)
- Canva(テンプレートによるデザイン)
- PowerPoint Designer(自動レイアウト提案機能)
- Notion(資料管理とコメント共有)
効果的なツールとして、ChatGPTやClaude等のAIツールによる文章作成支援、Canvaでのデザイン自動化、PowerPoint DesignerのAI機能活用が挙げられます。
これらを組み合わせることで、月20件の資料作成がある部署では、月160時間の工数削減が可能になります。
定量効果(目安)
- 作成時間:2時間→45分(約63%削減)(月160時間の工数削減となった場合、月40万円程度の削減)
- 修正回数:平均3回→1回(約67%削減)
- 営業満足度:主観評価で大幅向上(例:「わかりやすい」「早い」など)
定量効果として、人件費換算で月40万円のコスト削減、資料品質の向上による受注率5-10%アップ、営業担当者の商談時間確保による売上増加が期待できます。
初期投資は月1-2万円程度のツール費用のみで、ROIは3ヶ月以内に回収可能です。
7.商談資料効率化の導入ステップ

商談資料作成のAI活用導入を、段階的に進める具体的なステップを解説します。読者の皆さんがそのまま実践できるよう、詳細に説明していきますね。
【導入フェーズ】
- フェーズ1:準備(ステップ①②)
- フェーズ2:試行・検証(ステップ③)
- フェーズ3:定着・最適化(ステップ④⑤)
ステップ1:現状分析とテンプレート化(1-2週間)
まず、過去3ヶ月分の商談資料を収集し、共通パターンを抽出します。業界別、商品別、顧客規模別に分類し、それぞれの「勝ちパターン」を特定しましょう。
成約率の高い資料の構成や表現を分析し、3-5種類のテンプレートを作成します。
テンプレート例①:製造業向け 業務効率化提案(中小企業)
- 表紙:会社ロゴ+キャッチコピー
例)「業務のムダ、見直しませんか?」 - 現状の課題整理(例:紙ベース管理、情報分断)
- 解決策のご提案(クラウド管理システムの導入)
- 他社事例紹介(類似企業の改善効果)
- 導入による効果(コスト削減・業務時間短縮)
- 導入ステップ(初回ヒアリング〜運用開始)
- プラン・料金(スライド or 表)
- 質疑応答・次回ステップのご案内
テンプレート例②:BtoB企業向け 事例紹介に特化した資料提案
- キャッチ(例:「同業他社が導入した理由を公開!」)
- 導入前の課題と背景(Before)
- 導入プロセスと改善策(How)
- 定量成果(コスト/時間/売上)
- 顧客の声(インタビュー形式)
- 成功要因の整理と再現ポイント
- サービスの概要・支援体制
- 資料請求・お問い合わせ案内
テンプレート作成時は、変動部分を明確に定義することが重要です。「○○業界向け」「○○課題解決」など、穴埋め形式で対応できる箇所を特定し、AIが生成しやすい形に整理します。
ステップ2:AIツールの選定と環境整備(1週間)
ChatGPT Plus、Claude Pro、Microsoft Copilotなどから、自社の予算と機能要件に合うツールを選択します。
無料版があるツールもありますが、商用利用の場合は有料版を推奨します。
同時に、Canva Business、PowerPoint、Google Slidesなどのデザインツールとの連携環境を整備。クラウドストレージ(Google Drive、SharePoint等)での共有体制も構築します。
ステップ3:部分導入での検証(2-3週間)
いきなり全工程をAI化せず、まずは「文章の初稿作成」から始めます。顧客情報をAIに入力し、課題整理文や提案文の叩きを作成。人の手で、推敲・調整を行い品質を確認します。
ここではプロンプトの精度向上が成功の鍵です。
プロンプト例:提案文の初稿
♯命令書
あなたはプロのプロの優秀なライターです。以下の情報をもとに、商談資料の提案パートに使用できる文章の初稿を作成してください。構成は読み手が直感的に理解しやすく、ビジネス文書としての明瞭さと説得力を持たせてください。内容は指定の文字数制限内に収めてください。
【入力情報】
- 目的
商談資料の「提案パート」の原稿を作成するため - 対象
従業員30名の飲食店(個人経営・予約対応に人手がかかっている) - 背景・課題
電話予約や紙の管理台帳により、スタッフの業務負担が大きく、顧客情報も分散しているため、リピート促進施策が打てていない - 提案内容
予約・顧客管理を一元化するクラウドサービスを導入することで、受付業務を効率化し、顧客データを活用したリピート施策を可能にする - 出力形式
提案パートの文章(300字以内)
上記のような具体的な指示を心がけましょう。
ステップ4:ワークフローの標準化(1-2週間)
部分導入で効果を確認できたら、作業手順を標準化します。
「ヒアリングシート→AI入力→初稿生成→人間チェック→修正→完成」のフローをドキュメンテーションし、誰でも同じ品質で作業できる体制を整備します。
チェックリストも作成し、AIが生成した内容の確認ポイントを明文化。「事実確認済み」「顧客名に誤りなし」「数値データ正確」など、ミス防止のための仕組みを導入します。
ステップ5:全面展開と継続改善(1ヶ月以上)
標準化されたワークフローを全案件に適用し、効果測定を開始します。作成時間、修正回数、受注率などのKPIを設定し、月次で改善状況を把握。
AIの学習データとして、成功事例をデータベース化していきます。
継続改善では、新しいAI機能のキャッチアップも重要です。ChatGPTのプラグイン機能、PowerPointの新しいAI機能など、定期的にツールの進化をチェックし、さらなる効率化の可能性を探ります。
定期的な振り返りミーティングを実施し、現場の声を反映したプロセス改善を継続。半年後には、AI活用が当たり前の業務環境が構築されているはずです。
まとめ
「商談資料を作る」という作業は、営業成果を左右する戦略的タスクです。
AIを取り入れることで、“誰が作っても伝わる資料”が、短時間で作れるようになります。
急激な変化への抵抗感を和らげるため、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。「今日はAIのおかげで2時間早く帰れた」という実感を共有し、チーム全体のモチベーション向上につなげましょう。