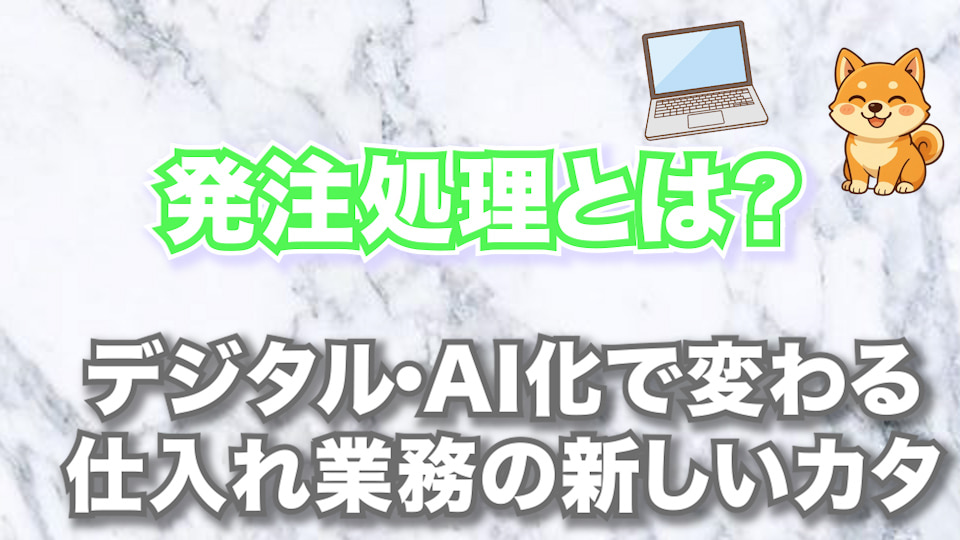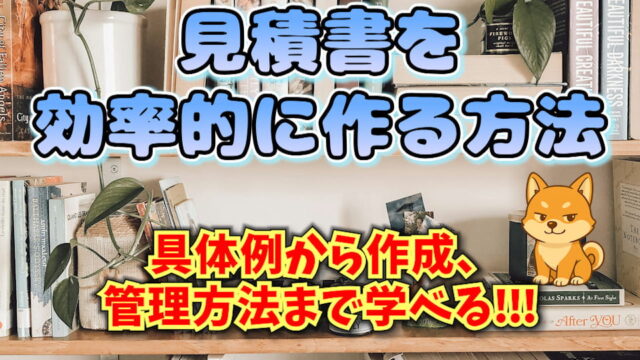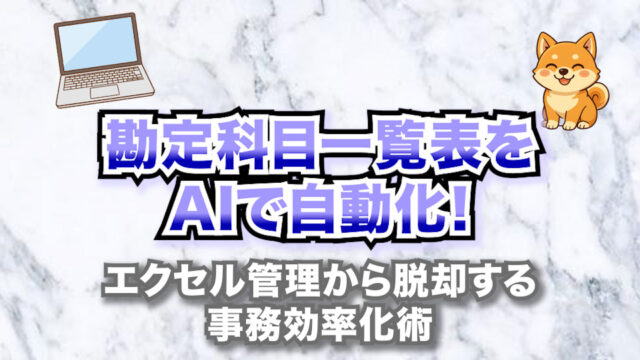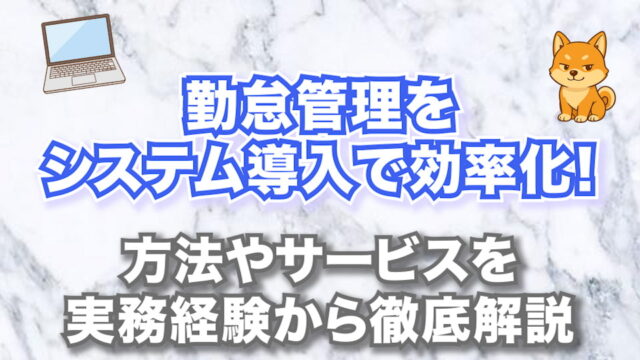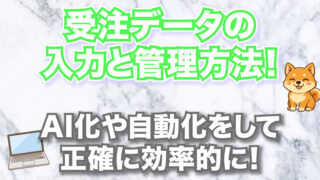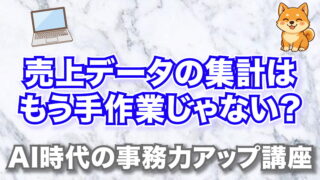発注処理は、企業が必要な商品やサービスを仕入れるために行う一連の業務プロセスです。
何気なくやっている発注処理ですが、しっかり管理、効率化していくことで、より価値をあげていくことができます。
実務ベースでデジタル化、効率化の方法について紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。
Contents
1.発注処理とは

発注処理は、企業が必要な商品やサービスを仕入れるために行う一連の業務プロセスです。
原材料、商品、備品、消耗品など様々なものを対象とし、会社の資金管理や生産計画に直結する重要業務です。
発注書は単なる「欲しいものリスト」ではなく、取引先との契約書に近い性質を持ちます。
金額の大小にかかわらず、正確性と透明性が求められる書類です。見積書や納品書、請求書などとは異なり、発注側が主体となって作成し、購入意思を明確に伝える書類という点が特徴的です。
発注処理が適切に行われないと、過剰在庫や欠品による機会損失、支払いトラブルなど多くの問題が発生します。
特に中小企業では、属人化しがちな業務でもあるため、効率化と標準化が課題となっています。
2.発注処理の基本構成と記載・実施項目

正確・迅速が命。ミスが連鎖を生むことも。
発注書や発注データには、以下のような基本項目があります:
| 項目 | 内容 |
| 発注先 | 仕入先名・担当者 |
| 発注日 | 発注書の作成日 |
| 品目・サービス名 | 商品コード・名称・スペック |
| 数量 | 単位付きで記載(例:10個) |
| 単価・金額 | 消費税区分含む |
| 納期 | 指定がある場合は明記 |
| 支払条件 | 締日・支払日・振込先など |
よくあるミスとその防止策
| よくあるミス | 防止策 |
| 数量・単価の入力ミス | ダブルチェック体制の構築、入力時の桁チェック |
| 納期設定の誤り | 生産計画・在庫管理と連動したシステム導入 |
| 承認プロセスの省略 | 権限設定を明確化、システムによる強制承認フロー |
| 発注書の未送付/二重送付 | 発注管理システムによる送付状況の可視化 |
| 特記事項の記載漏れ | テンプレート化と必須項目のシステムチェック |
3.発注処理の通常業務フロー

ルーティンだけど、地味に手間と確認が多い。
発注処理の一般的な流れは以下のとおりです。
1.社内申請→2.上長承認→3.発注書作成→4.送付→5.発注台帳への記録
特に時間がかかるのは、
- 見積比較
- 承認待ち
- 納期管理
のプロセスです。属人化しやすく、緊急性の高い発注では、承認待ち時間など業務のボトルネックになりがちです。
また、 Excel管理・メール送信・PDF化など、手作業が残っている会社もあったり、発注後の納期管理は担当者の経験と記憶に依存することが多く、全体的に属人化しやすい課題があります。
4.発注処理の管理・運用上の注意点

「どこに何を頼んだっけ?」が命取りになる前に。
発注管理の要は、履歴の見える化と検索性です。
整理・検索のコツ
- 発注書番号は「年月+連番」など検索しやすい形式に統一
- 取引先別・部署別・発注種類別でフォルダ分け
- 電子データと紙の二重管理を避け、原則電子化を徹底
- クラウドストレージの活用で場所を選ばず検索可能に
運用上の工夫
発注処理をスムーズかつ正確に行うためには、日々の運用にちょっとした工夫を取り入れることが効果的です。
まず、定期的に発注が必要な品目は、あらかじめリスト化しておくことで、発注忘れを防げます。特に消耗品や季節ごとに繰り返し注文する備品は、定期チェックのリマインドを仕組みに組み込むことで、うっかりミスが減ります。
次に、発注限度額(与信枠)の設定と管理も重要です。予算を超えた発注や不正防止の観点から、事前に金額上限を定めておき、超過する場合には別途承認が必要になるような運用ルールを設けておくと安心です。
また、緊急発注が必要になった場合の対応ルールもあらかじめ明確にしておきましょう。「誰が判断するのか」「通常フローを省略していいのか」「後追いでどう記録するのか」など、非常時こそ迷いなく動ける体制が求められます。
さらに、過去の発注履歴をデータベース化し、検索しやすく整理しておくことで、前回条件の再確認や同様案件の対応がスピーディになります。取引条件や価格の妥当性をすぐに把握できる環境があると、発注業務の質そのものが大きく向上します。
コンプライアンス面での注意点
- 業者選定の公平性確保(複数見積りの原則化)
- 発注権限の分離(発注依頼者と承認者の分離)
- 利益相反の回避(特定業者との癒着防止)
- 記録の適切な保存期間の設定(通常5〜7年)
また、納期管理や支払状況との連携も重要。発注書だけ管理していても、後工程(納品・請求)に繋がらなければ、業務を完結させることはできません。
5.どこがAIに?“全部やる”から“うまく分ける”へ。

手入力や確認作業は、もう“人がやらなくてもいい”領域。
発注処理は、「判断」が少なく、「定型的な情報処理」が中心。だからこそ、AIや自動化の得意分野がたくさんあります。
AIで置き換えやすい業務
- 発注書作成(フォーム入力→自動生成)
- 過去の発注履歴からの推奨品目の抽出
- 台帳記録(チャットボットからの自動転記)
- 発注先へのメール自動送信・PDF添付
- 納期リマインドの自動通知
人が残るべき業務
- 新規取引先の選定・交渉:信頼関係構築や質的評価
- 特殊・例外発注の判断:通常ルール外の状況への対応
- 最終承認と意思決定:重要案件や高額発注の最終判断
- トラブル対応:納品遅延や品質問題など予期せぬ事態への対応
- 戦略的発注計画:経営戦略に基づく調達方針の策定
「発注」という業務は、単純作業とみなされがちですが、実は企業の利益に直結する戦略的な側面を持っています。
AIを活用することで、人間は「何を、いくらで、いつ買うべきか」という本質的な判断により集中できるようになります。これからの事務職員には、データに基づく意思決定支援という新たな価値を提供する役割が期待されています。
つまり、人は“判断と交渉”に集中し、事務処理はAIに任せるスタイルへと変化していくことになります。
6.発注処理の業務効率化とオートメーションの具体策

ここからは、発注処理の業務効率化やオートメーションについて具体的に紹介していきます。
どの企業でも改善できる部分がありますので、ぜひ参考にしてください。
Before/After改善例
| 業務プロセス | Before | After | 効果 |
| 発注依頼受付 | メール・電話で受け付け、手動で発注書作成 | 専用フォームからの入力、自動転記 | 入力時間80%削減、転記ミス撲滅 |
| 承認プロセス | 紙の回覧、承認者不在で停滞 | モバイル承認、代理承認機能の活用 | 承認時間が2日→2時間に短縮 |
| 発注書送付 | 印刷→FAX送信→控え保管 | システムから自動送信、履歴自動保存 | 送付作業時間95%削減、紙代削減 |
| 納期管理 | 担当者がExcelで管理、確認忘れ | 自動リマインド、納期遅延予測機能 | 納期遅延30%減少、担当者負担軽減 |
| 発注分析 | 必要時に手動集計、傾向把握困難 | リアルタイムダッシュボード、AI予測 | 分析時間90%削減、コスト5%削減 |
活用できるツールと導入効果
発注処理の自動化・最適化には、以下のようなツールの導入が効果的です。目的に応じて段階的に取り入れることで、業務負担とミスの両方を大幅に削減できます。
| ツールカテゴリ | 代表的ツール | 導入効果(定量) |
| 調達・発注管理システム | SAP Ariba、Coupa、OBIC7購買管理 | 発注業務工数50〜70%削減、ペーパーレス化によるコスト年間10〜15万円削減 |
| RPA(業務自動化) | UiPath、Automation Anywhere、WinActor | 定型発注業務の自動化で、月40時間/人の作業削減 |
| AIによる発注最適化 | DataRobot、IBM Watson、Kintoneカスタム連携 | 在庫最適化で保管コスト15%削減、欠品リスク70%低減 |
| OCR・文書認識 | DocuWare、ABBYY FineReader、スキャンスナップ+Evernote | 紙文書の電子化で検索時間95%削減、保管スペース節約 |
| モバイル承認アプリ | kintone、Slack承認機能、Concur | 承認待ち時間80%削減、緊急発注への対応力アップ |
これらのツールは、単体でも効果がありますが、複数のツールを組み合わせることでシナジーが生まれ、より高度な効率化が実現できます。
たとえば「Googleフォームで依頼→Slackで承認→RPAで発注書作成→自動でPDF送付・記録」までをノーコード連携でつなげば、これまで1時間以上かかっていた作業が数分で完了するケースも珍しくありません。
7.発注処理の導入ステップ

“ひとつずつ整える”が、最速で一番ラクな道。
全自動化をいきなり目指すのではなく、段階的な導入が成功のカギです。
導入フロー
- 現状整理
- 発注処理のフロー図を作る
- どの工程が“手作業か”を明確にする - テンプレート・ルールの整備
- 発注書フォーマットを共通化
- 台帳の項目・書き方を全員統一 - 小さな自動化から始める
- Googleフォームで発注依頼を受け付ける
- 回答をスプレッドシートに連携
- ChatGPTで発注書を自動作成(gspreadなどと連携) - 通知・送信の自動化
- PDF作成+送付メールをZapierで自動化
- 納期のカレンダー登録&Slack通知も連携 - 定着と拡張
- 1ヶ月運用→フィードバック回収
- 発注処理だけでなく、納品・請求との連携へ拡張
STEP1:現状分析と課題の明確化(1〜2週間)
- 現在の発注プロセスを可視化する(フローチャート作成)
- 各ステップにかかる時間と工数を測定
- ボトルネックと非効率な部分を特定
- 発注データ(頻度・金額・取引先)を分析
- 具体的なゴール設定(例:発注処理時間50%削減、ミス率80%減)
実践ポイント: 1日のうち30分、自分の発注業務をストップウォッチで計測してみましょう。「あれ?この作業に15分もかかってるの?」という発見があるはずです。
STEP2:テンプレート化とルール整備(2〜4週間)
- 発注種類別のテンプレート作成(消耗品/備品/原材料/サービス別)
- 承認フローと権限の明確化(金額別・種類別)
- 発注コード体系の整備(商品・取引先・部署)
- 例外処理ルールの策定(緊急発注、特殊発注)
- 保存・管理ルールの標準化
実践ポイント: Google DriveやDropboxのような無料ツールで、まずはテンプレートを整備。「頻度別フォルダ」を作り、毎日使うものは最も見つけやすい場所に配置しましょう。
STEP3:小規模なAI・自動化の導入(1〜3ヶ月)
- 特定部署や発注種類を限定して試験導入
- 無料・低コストツールから開始(例:Googleフォーム+スプレッドシート連携)
- OCRツールで紙文書の電子化開始
- メール自動転送・自動返信の設定
- Excelマクロやシートの数式活用
実践ポイント:
無料のChatGPTを活用して、発注メールのテンプレート文を作成してみましょう。例えば「消耗品の発注を丁寧に伝えるビジネスメール」と指示するだけで使えるテンプレートが作れます。
STEP4:本格的なシステム導入と連携(3〜6ヶ月)
- 発注管理システムの選定と導入
- 既存システム(会計・在庫管理)との連携設定
- 取引先とのEDI(電子データ交換)構築
- モバイル承認機能の活用開始
- データ分析ダッシュボードの構築
実践ポイント:
システム導入前に必ず無料トライアル期間を活用し、実際の業務データで試してみましょう。特に「検索のしやすさ」「画面の見やすさ」は長期的に重要なポイントです。
STEP5:高度なAI活用と継続改善(6ヶ月〜)
- 発注パターン分析と自動提案機能の活用
- 予測発注モデルの構築と精度向上
- サプライヤー評価の自動化
- ダッシュボードによる調達戦略の可視化
- 定期的な運用レビューと改善サイクルの確立
実践ポイント:
月に一度、30分でいいので「今月削減できた時間」を計算してみましょう。例えば「1件あたり5分短縮×月100件=500分(8時間以上)の削減!」と具体的な成果を数字で示せると、上司や経営層への説得材料になります。
発注処理効率化を最小コストで始める方法

予算が限られている場合でも、次のステップで段階的に進められます。
- まずはGoogle WorkspaceやMicrosoft 365の既存ツールを最大活用
- Excelの関数やピボットテーブルで簡易的な分析開始
- 無料のタスク管理ツール(Trello等)で納期管理
- フリープランのChatGPTで定型文書作成を効率化
- 小さな成功事例を積み上げ、投資対効果を示して予算獲得
「一気にすべてを変える」のではなく、「小さく始めて成功体験を積み重ねる」アプローチが、特に中小企業では効果的です。発注処理のデジタル化は、単なる業務効率化ではなく、データに基づく経営判断を可能にするという大きな価値があります。
まとめ
デジタル時代の発注業務は、「作業」から「戦略」へと進化します。
AIに任せられる部分は思い切って任せ、人間にしかできない「判断」や「交渉」に時間を使うことで、事務職の仕事はよりクリエイティブで価値のあるものになっていくでしょう。
“発注処理は単なる事務”と思っていたらもったいない。
AIで省力化した分、「誰に頼むか」「どう交渉するか」に時間をかけられるようになれば、購買の価値は確実に上がります。
あなたの事務力は、これから“さらに活かせる時代”です。“やらないと回らない業務”から、“選んで価値を出す仕事”へ。
まずは、ひとつの発注書から、変えてみませんか?