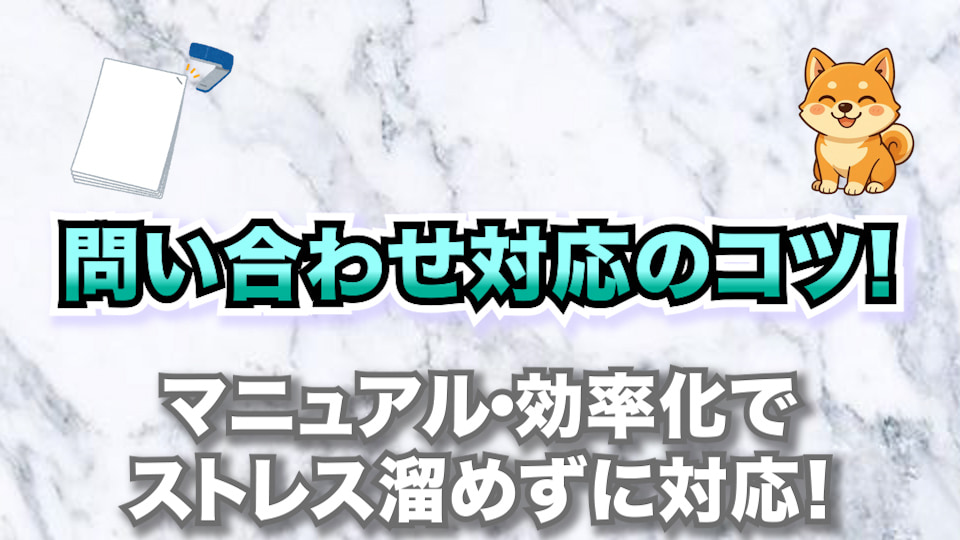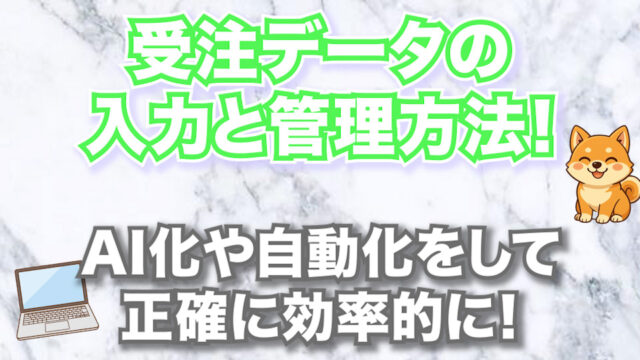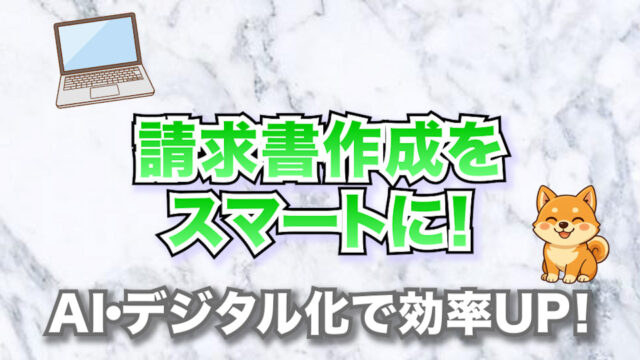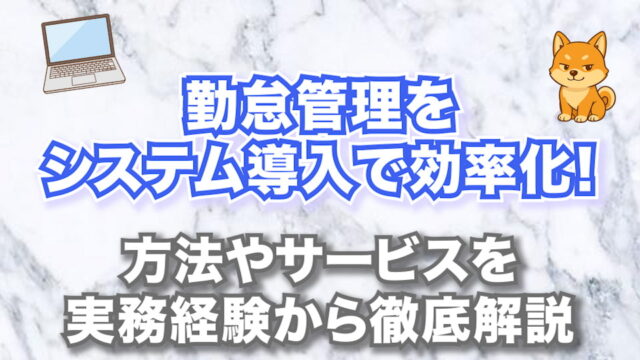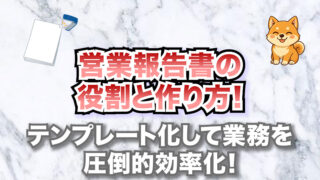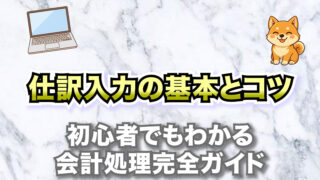問い合わせ対応とは、顧客や取引先、社内関係者からの電話やメールによる質問・要望に対して、正確かつ迅速に対応する業務です。
問い合わせされているということは、会社にとってチャンスであることが多いので、正しく管理していく必要があるでしょう。
今回は、そんな問い合わせ業務についてのコツやマニュアル・効率化について紹介していきます。
実務ベースで基本的な問い合わせ対応から、より正しく正確に行う方法まで紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
1.問い合わせ対応とは

問い合わせ対応とは、顧客や取引先、社内関係者からの電話やメールによる質問・要望に対して、正確かつ迅速に対応する業務です。
カスタマーサポートに近い印象を持たれがちですが、事務職では営業・経理・採用など多くの部門と関わりを持ちます。
他業務との違いは、「相手の意図をくみ取り」「的確に案内し」「履歴を残す」スキルが必要な点です。
リアルタイム性と感情的な要素が強く、単なる定型処理ではなく、気持ちに寄り添いながら複雑な状況を整理し、解決策を提示する力が求められます。
一次対応の質は会社の印象を左右し、信頼関係構築の接点となる戦略的業務です。営業が「攻めの顧客接点」なら、問い合わせ対応は「守りの顧客接点」。
既存顧客の継続利用や、新規顧客の安心感醸成に直結します。また、やり取りの中には、商品やサービスの改善点、新たなニーズの兆しが含まれており、顧客の声を拾い上げる重要な情報源でもあります。
2.問い合わせ対応の基本構成と実施項目

対応業務は、大きく以下の4ステップに分かれます。
- 【受信】電話やメールの内容を受け取る
- 【確認】必要な情報を聞き出す、または確認する
- 【回答】即答・調整・折り返しの判断と実行
- 【記録】対応履歴をシステムに入力・共有
よくあるミスと防止策
| ミスの種類 | 具体例 | 防止策 |
| 聞き取り不足 | 詳細確認せず推測で回答 | 5W1Hでの確認を徹底 |
| 回答遅延 | 社内確認で時間がかかる | 回答期限を最初に伝える |
| 情報共有漏れ | 他部署との連携不足 | 対応記録の標準化 |
| 感情的対応 | クレーム時の冷静さ欠如 | 対応マニュアルの整備 |
特に重要なのは、感情的になりがちな場面での冷静な対応です。相手の立場に立ちつつ、事実と感情を分けて整理することが解決への近道となります。
3.問い合わせ対応の通常業務フローと課題

一般的な問い合わせ対応フローは以下の通りです。
- 受付・初期対応(5分)
電話・メール・チャットで問い合わせを受け、基本情報(氏名・連絡先・用件)を確認します。 - 内容整理・分類(10分)
問い合わせ内容を5W1Hで整理し、緊急度・重要度で分類。必要に応じて関連部署への連絡を行います。 - 調査・確認(30分〜2時間)
社内システムでの情報確認、関係部署への問い合わせ、過去の対応事例の調査を実施します。 - 回答作成(15分)
相手に応じた適切な文体・内容で回答を作成。必要に応じて上司チェックを受けます。 - 回答・フォロー(5分)
回答の送信・連絡と、必要に応じたフォローアップを行います。
主な課題と時間のかかる工程
- 社内確認で関係者が不在・多忙(最大半日待機)
- 過去の対応事例検索に時間がかかる(20分〜1時間)
- 複雑な案件での回答内容検討(1時間〜)
- 感情的な相手への対応で精神的疲労蓄積
これらの課題により、1件あたり平均1.5時間、複雑な案件では半日以上要することも珍しくありません。
課題としては、「誰が対応すべきか」の判断があいまいになりやすく、属人化しがちです。電話対応では手が離せない場面で着信に気づけない、メールでは返信が後回しになるといった、即時性の欠如も悩ましいポイントです。
4.問い合わせ対応の管理・運用上の注意点

問い合わせ対応をスムーズに行うには、組織として工夫した管理体制を持つことが不可欠です。
FAQと履歴の活用
よくある質問(FAQ)をまとめたデータベースを作ったり、過去の対応内容をキーワードで検索できるようにすることで、スムーズに対応できるようになります。
あらかじめ文面を整えたテンプレートを用意しておくことで、毎回ゼロから考える必要がなくなり、対応の質を均一に保ちつつ、対応時間を大幅に短縮できます。
すぐに答えを見つけられる仕組みがあれば、ミスも減って安心。
情報共有とナレッジ蓄積
対応内容はフォーマットに記録し、社内で共有することが重要です。
成功例だけでなく、対応が難しかったケースやクレーム事例なども蓄積することで、チーム全体のスキルアップと、再発防止の仕組みづくりに役立ちます。
振り分けルールの整備
問い合わせをカテゴリー別に分類し、担当者の専門性を活かすことで、対応の効率と質を同時に高めることができます。また、即日・3日以内・1週間以内に対応するなど優先順位付けも重要です。
さらに、対応済・未対応の可視化も重要です。対応漏れを防ぐためには、タグ付けや対応ステータスの更新が必須。可能であれば、専用ツールやチャットボットとの連携も検討しましょう。
5.どこがAIに?“全部やる”から“うまく分ける”へ。

問い合わせ対応におけるAI活用のポイントは、人とAIの得意分野を理解し、適切に役割分担することです。
AIに置き換え可能な部分
- よくある問い合わせの自動返信(例:営業時間、所在地、料金)
- メール本文から要点を抽出し、定型文を自動生成
- 問い合わせ内容の自動振り分け・タグ付け
- 対応履歴の自動記録・整理
- 感情分析による優先度判定
人がやるべき対応
- 複雑な状況の整理・判断
- 感情的な相手への共感・寄り添い
- 創造的な解決策の提案
- 企業方針に関わる重要な判断
- 個別事情を考慮したカスタマイズ対応
- 長期的な関係構築を見据えた対応
“AIに全部やらせる”のではなく、“人が価値を発揮すべき領域に集中するためのAI活用”が、これからのスタンダードです。
6.問い合わせ対応の業務効率化とオートメーションの具体策

ここからは、問い合わせ対応の業務効率化、オートメーションについて紹介していきます。
より正しく効率的に問い合わせ対応できる方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
Before/After改善例
| 項目 | Before(従来) | After(AI活用) | 改善効果 |
| よくある質問対応 | 都度検索しながら手入力(約30分) | FAQ+自動返信システムで即時対応(約1分) | 約96.7%短縮 |
| 初回回答時間 | 担当者が空くまで2時間 | 自動返信 or タスク通知により15分で初動 | 約87.5%短縮 |
| 対応記録の作成 | 手入力で記録ミス・漏れも発生(約15分) | 音声→テキスト変換+CRM自動記録(約1分) | 約93.3%短縮 |
| 担当者の振り分け | 内容を読んで手動判断(約10分) | カテゴリ自動分類で瞬時に割り当て(約1分) | 約90%短縮 |
| 未対応タスクの管理 | メールフラグや付箋で手動チェック | タスク管理+Slack通知で可視化 | 対応漏れゼロ化 |
| 月間対応件数 | 約200件 | 自動化+再利用により500件へ増加 | 約150%向上 |
使えるツール例
- ChatGPT:メール返信文の下書き作成
- Googleフォーム:電話問い合わせのログ記録フォーム化
- Notion / esa:FAQのナレッジベース整備
- Zendesk / Re:amaze:顧客対応一元化ツール
- CRM(Hubspot / Salesforceなど):対応履歴と連携
定量効果(一例)
- 時間削減: 1件対応あたり平均1.5時間→0.3時間(80%削減)
- コスト削減: 月間人件費30万円→15万円(50%削減)
- 精度向上: 回答ミス率15%→3%(80%改善)
- 顧客満足度: 70%→85%(15ポイント向上)
7.問い合わせ対応効率化の導入ステップ

以下の手順で進めれば、誰でも問い合わせ対応業務にAIを導入できます。
段階的な導入が成功の鍵。以下の7ステップで着実に進めましょう。
Step1: 現状分析とデータ収集(1週間)
まず、現在の問い合わせ対応の実態を把握します。1週間分の問い合わせ内容・対応時間・結果を記録し、問い合わせの種類別に分類してください。Excelで「日時・問い合わせ内容・分類・対応時間・結果」の5列で管理すると後の分析が楽になります。
Step2: FAQ作成とテンプレート化(2週間)
収集したデータから、頻出する質問TOP20を抽出し、それぞれに対する標準回答を作成します。この際、「お忙しい中お問い合わせいただき、ありがとうございます」などの定型挨拶も含めた完全な回答文として整備しましょう。
Step3: 分類ルールの策定(1週間)
問い合わせを「緊急度」(即日・3日以内・1週間以内)と「分野」(商品・サービス・請求・苦情)の2軸で分類するルールを作成。各分類の判断基準を明文化し、誰が見ても同じ判断ができるようにします。
Step4: 簡易チャットボット導入(2週間)
無料または低価格のチャットボットツール(ChatworkやSlackのBot機能など)を使用し、FAQ TOP10への自動回答機能を実装します。まずは社内テストを1週間実施し、問題なければ顧客向けに公開します。
Step5: 問い合わせ管理システム導入(3週間)
GoogleフォームとGoogleスプレッドシートを連携させた簡易的な管理システムを構築。問い合わせをフォーム経由で受け付け、自動的にスプレッドシートに記録されるようにします。この際、分類・優先度・担当者・ステータスの列も追加し、進捗管理を可能にします。
Step6: AI文章生成ツール活用(2週間)
ChatGPTやClaude等のAIツールを使用した回答文作成の仕組みを導入。「以下の問い合わせに対して、丁寧で分かりやすい回答文を作成してください。トーンは親しみやすく、ビジネス文書として適切な形式で」というプロンプトテンプレートを作成し、チーム全体で活用します。
Step7: 高度な自動化導入(4週間)
本格的な問い合わせ管理システム(ZendeskやFreshdesk等)の導入を検討。自動分類・エスカレーション・レポート機能などを活用し、より高度な自動化を実現します。
運用定着のポイント
- 週次で効果測定を実施し、改善点を随時調整
- チーム内でのナレッジ共有会を月1回開催
- 顧客からのフィードバックを積極的に収集し、システム改善に反映
- 新しいツールは必ず「小規模に」「テスト導入」から開始し、問題がないことを確認してから本格導入
注意すべきポイント
- 完璧を求めすぎず、70%の精度でも導入を優先
- 従来の手作業と並行運用期間を設け、リスクを最小化
- スタッフのAIリテラシー向上のための研修時間を確保
- 顧客への案内(「現在システム改善中のため、回答にお時間をいただく場合があります」等)を事前に行う
この7ステップを着実に実行することで、約3ヶ月後には従来比80%の時間短縮と、顧客満足度の大幅向上を実現できます。
重要なのは、一気にすべてを変えようとせず、できるところから確実に改善していく姿勢です。
問い合わせ対応は、「小さな仕事」に見えて、企業の信頼を支える「大きな仕事」です。その質を保ちつつ、AIの力でストレスを減らせたら、事務の未来はもっと楽しく、もっと誇れるものになるはずです。
まとめ
問い合わせ対応は、属人的になりがちですが、しっかり管理をすることで、会社がいい方向に進みます。
特に問い合わせしてきているということは、何かしら会社に興味を持っているとのことなので、ここをしっかりしていくだけでもかなり変わってくるでしょう。
今回紹介した内容から、ぜひ取り入れやすい部分から取り入れていってくださいね。