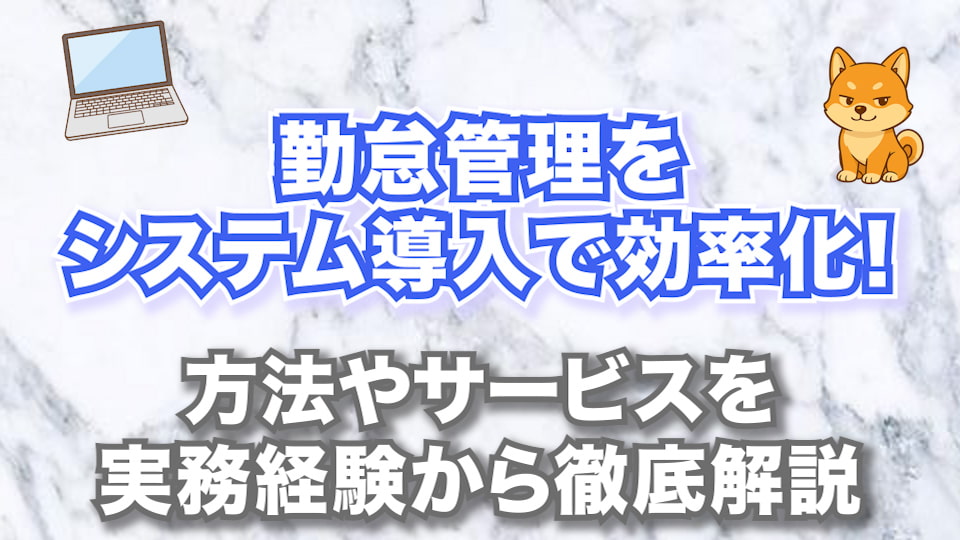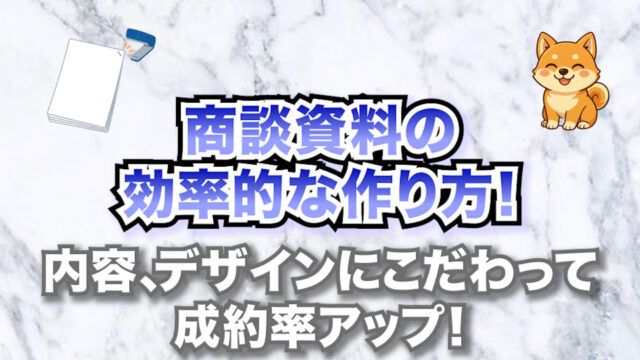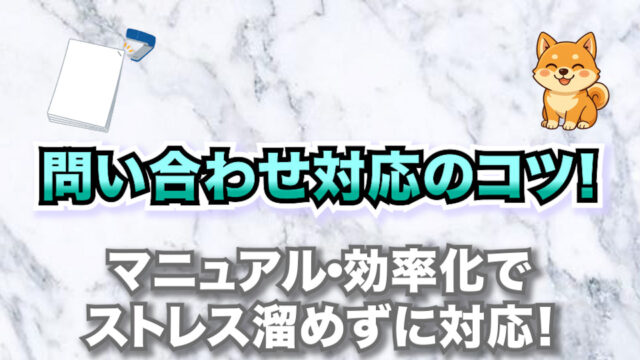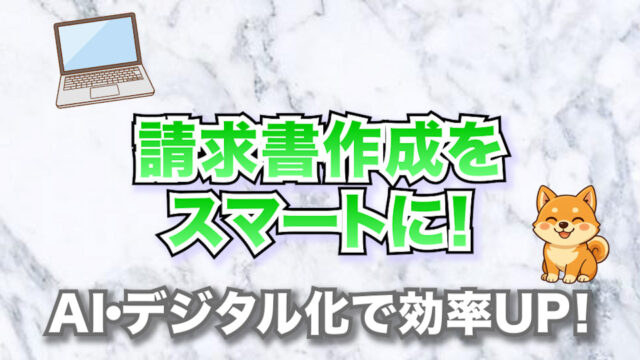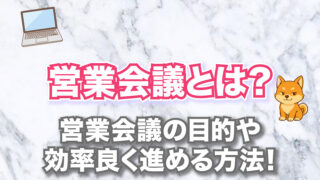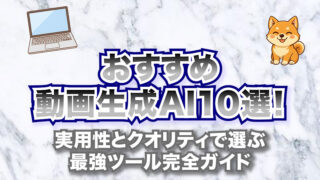毎月の勤怠集計で残業続き、有休申請の承認漏れでトラブル発生…そんな経験ありませんか?
勤怠管理は、大きい会社であればあるほど、骨が折れるもの。
今回は、そんな勤怠管理を効率的に正確に行う方法について紹介していきます。
費用をしっかりかけて最適化する方法から、費用をかけずとも効率化する方法まで、実務ベースで紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
1.勤怠管理とは

勤怠管理は、働き方の“見える化”を支える、事務の要です。
勤怠管理が担う4つの役割
- 労働基準法の遵守:36協定の上限管理、有給休暇の付与・管理
- 給与計算の基礎データ提供:正確な労働時間に基づく賃金支払い
- 労働生産性の把握:部署別・個人別の働き方分析
- 従業員の健康管理:長時間労働の防止、働き方改革の推進
勤怠管理とは、従業員の出勤・退勤時刻、休暇、残業、休日出勤などの勤務実績を記録・把握する業務です。
給与計算や労働時間管理の土台となる情報を扱うため、正確性とタイムリーさが求められます。
間違いやすい業務
- 給与計算:勤怠データをもとに金額を算出
- 人事管理:人材配置・評価などの戦略領域
- 勤怠管理:労働時間の「記録・確認・集計」担当
特に給与計算との連携では、勤怠データの誤りが直接給与ミスにつながるため、正確性が極めて重要です。
また、労基法遵守や働き方改革の実現に直結する、企業経営にも関わる重要業務です。
2.勤怠管理の基本構成と記載項目
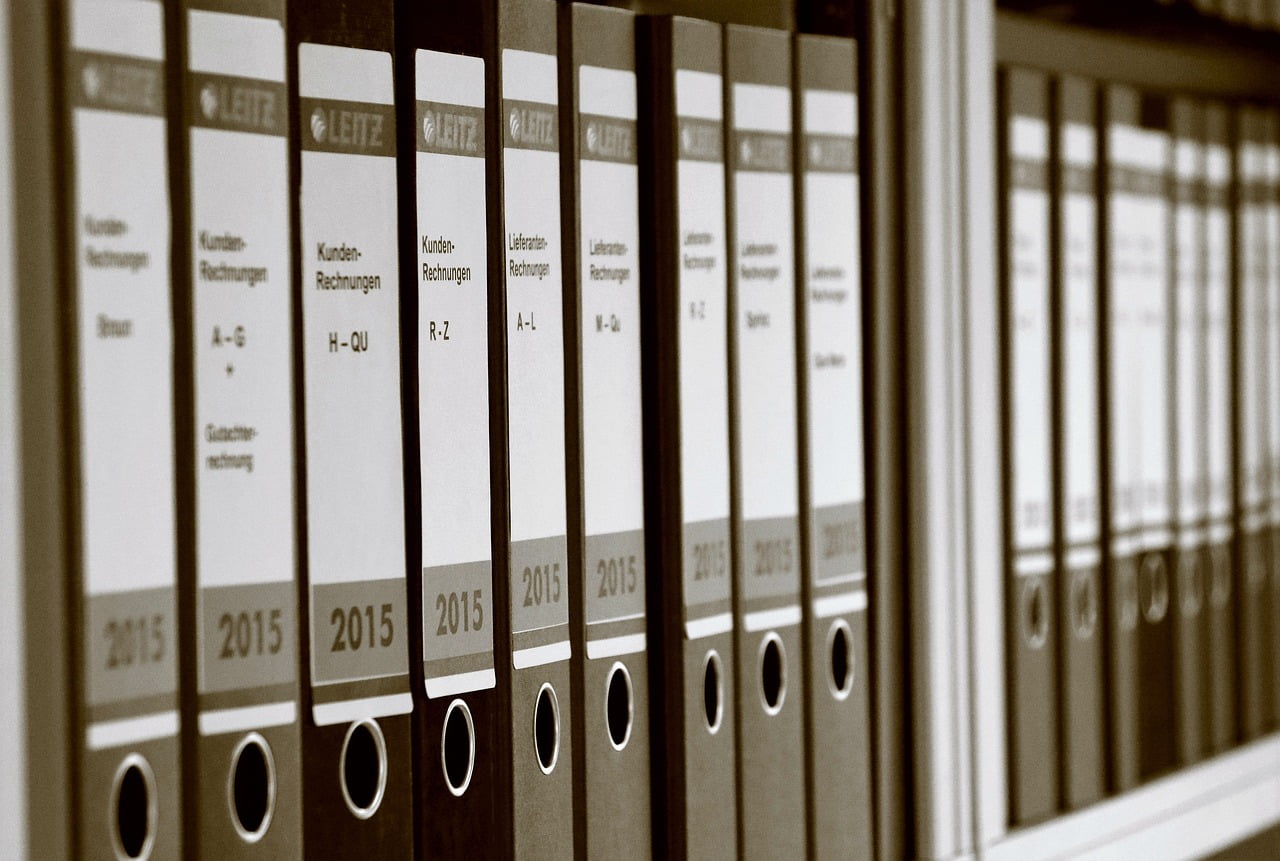
勤怠管理の基本は「正確に記録し、確実に確認すること」。
本章では、最低限押さえておきたい必須項目から、管理レベルを高める追加項目までを整理し、よくあるミスとその防止策もあわせて解説します。
必須の記録内容
- 出勤・退勤時刻
- 休憩時間
- 実労働時間
- 残業時間(法定内・法定外)
- 休暇取得状況(有給、特別休暇)
- 遅刻・早退・欠勤
また、労基法(以下、法)に基づき、最低限の勤怠項目を押さえるだけでなく、働き方の多様化や法令対応の観点から、以下の項目もあわせて管理しておくと実務上のトラブル防止や制度整備に役立ちます。
管理レベルを上げる追加項目
- 在宅勤務・テレワーク時間
自宅勤務時も始業・終業時刻の記録が必要。(法32条/労働時間等) - 時間外労働の事前申請・承認
残業には事前申請・承認が必須。36協定の範囲内で管理。(法36条/時間外及び休日労働)
- 休憩時間の詳細(分割取得など)
休憩は労働時間に応じて付与が必要。取得状況も明確に。(法34条/休憩)
よくあるミスとその防止策
頻発する3大ミス
- 打刻漏れ・打刻ミス
- 原因:手動入力、紙のタイムカード使用
- 防止策:ICカード打刻、スマホアプリ導入
- 残業時間の計算間違い
- 原因:法定内・法定外の区別、深夜割増の計算ミス
- 防止策:自動計算システムの導入、チェックリストの活用
- 有給休暇の管理漏れ
- 原因:付与日の把握不足、取得義務化への対応遅れ
- 防止策:自動付与システム、取得促進アラート機能
記録と承認、そして給与との連携をいかにスムーズにするかが肝です。
3.勤怠管理の通常業務フロー

ここからは、勤怠管理の通常業務フローについて紹介していきます。
まずはこのフローをしっかり確認した上で、改善に取り組んでいきましょう。
月次勤怠管理サイクル
日次作業:打刻確認・異常チェック(10分/日)
↓
週次作業:残業時間の集計・承認(30分/週)
↓
月次作業:月末締め・データ確定(4時間/月)
↓
給与計算部門への引き継ぎ(1時間/月)
このうち3〜5の工程はとくに時間がかかり、記録の曖昧さ・ルールの不統一がボトルネックになります。
課題と時間を奪う工程
5つのボトルネック
- 打刻データの目視チェック(40分/日)
100名規模なら毎日1時間以上の確認作業 - 残業申請と実績の突合(2時間/週)
申請書と実際の勤務時間の照合作業 - 有給取得状況の個別管理(1時間/週)
Excelでの残日数計算と更新 - 月末の集計・修正作業(6時間/月)
計算ミスの発見と修正の繰り返し - 各部門への確認・催促(2時間/月)
承認漏れや修正依頼の個別対応
勤怠管理は日々の確認と月末の集計が重なりやすく、特に人の手に頼る部分が多いほど工数やミスが発生しやすくなります。
目視確認や手動集計など、日ごろに行っている作業の中に、実は見直すべき非効率が潜んでいます。
次は、そうしたムダを減らすための運用上の注意点を整理していきます。
4.勤怠管理の管理・運用上の注意点

ここからは、勤怠管理の管理・運用上の注意について紹介していきます。
管理のポイント
- フォーマット・形式の統一
- 検索性の向上
- 関連書類(出勤簿、休暇申請書、残業申請)の紐づけ
法令遵守のためのチェックポイント
- 月45時間、年360時間の残業上限
- 有給5日取得義務の履行状況
- 深夜・休日労働の割増計算
- 労働時間の記録保存(3年間)
検索しやすい状態に保つ=確認・修正のストレス軽減に直結します。
5.どこがAIに?“全部やる”から“うまく分ける”へ。

勤怠管理では、分業がカギとなります。
打刻確認・残業集計・承認などの工程を役割ごとに明確に分けることで、業務の属人化を防ぎ、ミスや対応漏れのリスクを大幅に減らすことができます。
AIで代替できる部分
- 打刻記録の自動収集(スマホ・IC・顔認証)
- 遅刻・早退・残業などのルールベースでの異常検知
- 有休取得の残数自動更新とアラート通知
- 月次レポートの自動集計
人が担うべき部分
- 状況判断:特殊な勤務形態への対応、例外処理
- コミュニケーション:従業員との相談対応、管理職への提案
- 改善提案:業務フローの見直し、制度設計
- 戦略的分析:働き方改革の企画、生産性向上施策の立案
- 関係構築:他部署との調整、外部機関との対応
AIは「正確で繰り返し可能な処理」に強い。人は「例外対応と信頼構築」に価値がある。
この特性を生かした線引きこそ、事務の新しい力になります。
6.勤怠管理の業務効率化とオートメーションの具体策

Before/Afterで変化を可視化すると、業務改善の効果が明確になります。ここでは、効率化と自動化の具体策を紹介します。
Before/After改善例
| 業務項目 | Before(手作業) | After(AI活用) | 改善効果 |
| 日次打刻チェック | 目視確認40分 | 自動アラート5分 | 87.5%短縮 |
| 残業申請照合 | Excel突合2時間 | 自動照合10分 | 91.7%短縮 |
| 月次集計作業 | 手計算6時間 | 自動集計30分 | 91.7%短縮 |
| 有給管理 | 個別計算1時間 | 自動付与・残高管理5分 | 91.7%短縮 |
| レポート作成 | PowerPoint作成3時間 | 自動生成15分 | 91.7%短縮 |
価格別ツールと導入効果
無料で使える
- HRMOS勤怠:打刻〜集計の基本自動化
- 効果:月10〜15時間の作業削減、確認ミスの軽減にも貢献
月5万円以下(基本自動化)
- ジョブカン勤怠管理:打刻〜集計の基本自動化
- 効果:月20時間削減、ミス90%減少
Level 2:高度自動化(月10万円以下)
- TeamSpirit:AI異常検知、予実管理
- 効果:月35時間削減、法令違反リスク95%減少
Level 3:完全自動化(月15万円以下)
- キングオブタイム + RPA:完全無人化
- 効果:月50時間削減、精度99.5%向上
※効果には個人差があります
7.勤怠管理効率化の導入ステップ

ここからは、勤怠管理を効率化していくためのステップについて紹介していきます。
少し面倒ではあるものの、全く難しいものではないので、一つ一つ行なっていき、勤怠管理の効率を上げていきましょう。
Phase1:準備・設計(1ヶ月目)
Week1:現状分析
- 現在の勤怠管理業務を時間計測
- 日次作業:打刻確認、異常対応
- 週次作業:集計、承認業務
- 月次作業:締め処理、レポート作成
- 問題点の洗い出し
- 時間のかかる作業TOP5をリストアップ
- ミス発生箇所の特定
- 目標設定
- 削減したい作業時間の明確化
- 改善したい精度レベルの決定
Week2-3:要件定義
必須機能チェックリスト
- Web打刻機能
- 自動集計機能
- アラート機能
- 承認ワークフロー
- レポート自動生成
- 給与システム連携
運用ルールの策定
- 打刻時間(出社前30分〜退社後1時間など)
- 修正申請の承認フロー
- 例外処理の対応方法
Week4:ツール選定
- 3社以上のツールを比較検討
- 無料トライアルの実施
- 費用対効果の算出
- 導入ツールの決定
Phase2:部分導入(2-3ヶ月目)
Month2:パイロット運用
- 特定部署(10-20名)でのテスト運用
- 従来方式との並行運用
- 問題点の洗い出しと改善
- マニュアルの作成・修正
操作マニュアル作成のポイント
- スクリーンショット付きの手順書
- よくある質問(FAQ)の整備
- 緊急時の連絡先・対応方法
- 新入社員向けの簡易版マニュアル
Phase3:全社展開(4-5ヶ月目)
Month4:段階的展開
- 部署別の導入スケジュール作成
- 各部署への説明会実施(1時間×部署数)
- 操作研修の実施(30分×3回)
- サポートデスクの設置
Month5:運用定着
- 全社運用開始
- 従来システムの停止
- 効果測定とレポート作成
- 更なる改善点の特定
Phase4:高度化・最適化(6ヶ月目以降)
継続的改善のサイクル
- 月次レビュー
- 削減時間の測定
- ミス発生状況の確認
- ユーザー満足度調査
- 四半期見直し
- 新機能の検討
- 運用ルールの最適化
- 他システムとの連携拡大
- 年次戦略策定
- より高度なAI機能の導入検討
- 働き方改革施策との連携
- 次年度の投資計画策定
成功のための重要ポイント
導入成功の5つの鉄則
- 経営層のコミット:トップダウンでの推進意志表明
- 段階的導入:いきなり全社ではなく、スモールスタート
- 十分な研修:操作方法だけでなく、業務変更の意義も共有
- 継続的サポート:導入後3ヶ月は重点的なフォロー体制
- 効果の見える化:定量的な改善効果を定期的に共有
まとめ:AI時代の“事務力”とは
今回は、勤怠管理の基本的な方法やAIによる効率化方法について紹介しました。
勤怠管理のAI化は、単なる「効率化」を超えて、事務職の働き方そのものを変革します。
ルーティンワークから解放された時間を、より戦略的で創造的な業務に充てることで、あなたの市場価値は確実に向上します。